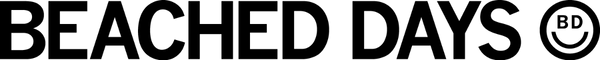第4回 ハービー・フレッチャー The Thrill is Back〜ボードカルチャーの第一人者
Share
サーフィンの世界で最もクールなことの一つは、時代を切り開いたパイオニア(先駆者)から、リアルなストーリーを直接聞けること。なかでも世界中で老若男女を問わず、同じフィールドで楽しめるサーフィンは唯一無二のもの。果たしてそれがスポーツであるのか、否か、カルチャーなのか。BEACHED DAYS的には間違いなく後者と考えます。
去る5月、ロンハーマン千駄ヶ谷店のアートイベント『Take Five』の開催のために来日したハービー・フレッチャー。ボードカルチャーを作り出した第一人者であり、いまも現役の正真正銘のレジェンド。そして、ミッチ・アブシャーやジョエル・チューダーのメンターとしても知られ、90年代のロングボード・リバイバルの第一人者でもあります。数々の肩書き、功績は枚挙にいとまがないのですが、膨大なストーリーの中よりその一部を伺った。

(Maalaea, Maui 1976. Photo: Art Brewer)
今回はロンハーマンでのアートショー『Take Five』の開催がメインの目的と伺っていますが、実に何年ぶりの来日になりますか?
前回は確か5年位前で、グリーンルーム・フェスティバルのために来た。先日のロンハーマンでのアートショーは本当にいいイベントで、大成功だったんじゃないかな。展示した私の写真や映像も来場者からとても良いフィードバックをもらったしね。
『Take Five』というショーのタイトルとコンセプトはどこから?
子供の頃からいつもデイブ・ブルーベックのジャズを聴いていて、なかでも彼の曲Take Fiveが好きだったんだ。タイトルもサーフィンのハンギング・ファイブを思い起こすだろ。


(『Take Five』by Herbie Fletcher Photo courtesy of RHC)
アートショーでは、サーフィンのヒストリーを感じられる写真も多く飾られていて圧巻でした。
ああ、あれらは古いものから新しいものまでを展示した。新しいものといっても7,8年前だな。古いものは1950年代の夏、義父のウォルター・ホフマンが撮影し、私が譲り受けたもの。彼は1951年のマカハ・サーフコンテストのチャンピオンで、普段は織物業を営む父親のもとで働きながらサーフィンをし、夜は海軍のラジオ局で働いていた。私が妻のディビに出会ったのは、1964年のマカハのビーチだった。
写真だけでなく、アートはこれまで私の人生の多くを占めている。でも、サーフィンを決して諦めたことはなく、それが私のアートにも大きな影響を与えている。
ここ日本ではやっと第3世代のサーファーが出てきた状況ですが、あなたのサーフファミリーはなんと4世代にも渡っていますね。
我々は単なるサーファーじゃなくて4世代に渡るチャンピオンだ。ウォルターはビッグウェイブ・サーフのパイオニア。その娘でディビの姉であるジョイス・ホフマンは4xウィメン・ワールドチャンピオンで、彼女は女性の世界のサーフィンを変え、サーフィンにスタイルを取り入れた1人。私の世代はフィル・エドワーズからサーフィンを学び、彼を通じてウォルター、そしてディビに出会った。
(ハービーの息子はご存じ、エアリアルのパイオニアのクリスチャンとビッグウェイバーでありエクストリーム・サーフィンの第一人者、ネイザン。)
そして、孫のグレイソンやレーザー、ジェットソンも皆サーフ、スケート、スノーボードをやっている。
写真にもあるハワイ・ノースショアのオリジナル・パイプハウスについて教えて下さい。
パイプラインは私にとってお気に入りの場所で、長きに渡りずっと住んできた。初めてパイプラインでサーフィンしたのが、1965年だから今から約60年前のことだな。ファット・ポール(ポール・ピーターソン)がかつてのジェリー・ロペスの家の後ろの区画に住んでいて、1980年にジェリーがパイプハウスを建て、共同で家を所有していた。97年に売却し、いまはボルコム・ハウスになっているけど、家の前には広い庭があって、パイプでサーフィンした後はいつもそこでハングアウトしていた。これは今も昔も変わらないね。いまファット・ポールの住んでいた土地には、ジェイミー・オブライエンの大きな家が建っている。

(w/Gerry and BK. Sunset 1971. Photo: Jeff Divine)
当時はあのジミー・ヘンドリックスとも一緒につるんでいたと聞きました。彼のギターの演奏をバックグラウンドにビーチでサーフィンをしていたというのは本当ですか。
ああ、ジミー・ヘンドリックスとは1967年のモンタレー・ポップ・フェスティバル(ヒッピームーブメントの歴史的イベント、『Summer of Love』)で出会い、マイク・ヒンソンやアンディー・ウォーホールのミューズと一緒に1970年にマウイのレインボーブリッジのコンサートのムービーに出演している。ジミーは音楽の歴史を変えた張本人だ。そう、ロッキーポイントでジミーがギターを弾くのを聞きながら、サーフィンしていたのは事実さ(笑)。
これまで数々のインタビューを受けて来たと思いますが、読者にあなたが掲げたスローガン『The Thrill is Back』についてあらためて教えてください。
1967年はゲイリー・チャップマンとオフザウォールに住んでいた。当時、サーファーたちは、パイプラインをビーチパーク側からチェックし、良くないと思うと他の場所に行っていた。でも、バックドア、オフザウォールでは時にパーフェクトなライトのチューブがブレイクしてたのさ。ゲイリーはディック・ブルーワーとミニガンを開発していて、自分も一緒にその速いチューブを抜けるボードを作って、波を駆け抜けていた。
後にクリスチャンが生まれ、学校に行かせるためにカリフォルニアへと移り住むことになったんだけど、1970年代はショートボード全盛の時代。ハワイと比べて、カリフォルニアの波は力が弱すぎてショートでやるのには無理があった。小さい子供がやるには問題無かったけど、大の大人には小さすぎた。商業的にも誰もロングボードに見向きもしない時代だったけど、『The Thrill is Back』というスローガンを掲げ、ロングを再び流行らせることが革命だと思ってやってきた。ロングのフォームを手に入れるのが困難な時代だったけど、1975年にHerbie Flecther Surfboardsをダナポイントで立ち上げ、人々にロングボードを提供してきた。1976年にAstrodeckを作ると、グリップ力が格段に増し、サーファー達のマニューバーが格段に進化した。クリスチャンはスケートボードのマニューバーをサーフィンに取り入れ、エアリアルをやり出した。一方、ネイザンはクリスチャンがやるエアーのすべてをマスターしていたけど、トム・キャロルのようなハードなターンをして、ビッグウェイブに挑んでいた。
あなたはロングボードに乗って、単にレイドバックするのではなく、サーフィンの進化に携わってきました。『Side Slip Boogie』のマニューバーはどのようにして生まれたのですか? ブルース・アイアンズはかつてあなたとのタヒチのサーフトリップで、チューブの中でサイドスリップをしていたのが印象的です。
サイドスリップはチューブでストールし、コントロールできる効果的なマニューバーだ。1966年にマウイのホノルア・ベイの波の大きな日に、フィル・エドワーズの作ったサーフボードでハングテンをしていたら、リバース・パインフィンが抜けてスライドして横滑りを始めた。フィルに伝えると、「ああ、それがハングテンとサイドスリップのことだ」と言っていた。それから私は練習を始めて、サイドスリップしてストールし、またフィンを入れてチューブライドをコントロールする方法を学んだ。大きなボードで大きなフィンを使い、速くてホローな波でやるのが俺のスタイルだ。

(Wrecktangles 2023 Photo courtesy of RHC)
今のサーフィンを取り巻く環境についてどう思いますか?
そうだな、サーフィンインダストリーはすでにDone、終焉を迎えたと思う。多くの人々がサーフィン業界のビジネスに手を出し、今はすべてのブランドを所有するカンパニーが1 つという状況。実際にはサーフボードを作る人達もいて、小さなカンパニーはあるけどソウル(魂)は失われてしまった。サーフィンがメジャーになって、メインストリームだけしかない状況はなんだか恐ろしい気がする。
でもいま、キッズ達がこのソウルの部分に戻り、ルーツに戻って変化の兆しも見えていて、それがまたビッグサークル(大きな輪)になっているようにも思う。パイプラインで折れたボードを集めて、Wrecktangles(壊れてもつれたもの)を作ったコンセプトもそこにある。
かつてサーフィン界には多くのキャラクターがいたけれど、いまは個性やスタイルも関係なくなってしまったな。私が見たサーフィン界で最後のキャラクターは、ブルース・アイアンズだ。クリスチャンやアーチー(マット・アーチボルド)、アンディ・アイアンズらは、ザラザラとした個性を持っていたよ。WSLのコンテスト、賞金主義が、サーフィンを単なるスポーツにしてしまったのさ。オリンピックを含めてね。ソウル(魂)は失われてしまったよ。
かつてのコンテストは、誰もが楽しい時間を過ごし、交流することを楽しんでいてアロハの精神もあった。コンテストであっても、勝ち負けだけを気にするんじゃなく、クリエイティブな部分、お互いにどんなボードをシェイプしているのかなどをチェックしていた。
今後はサーフボードのシェイプも再開するつもりだ。シェイピングも自分にとってはアートで、グラシッングでレジンペイントを施す。ペインティングや大きな彫刻、写真や映像を手がけてきたのもサーフィンの延長線にあるアートなのさ。
長きに渡り、サーフィンに向き合ってこられましたが、サーフィンや海がない生活することは考えられますか?
サーフィンなしで生きていくことは想像もつかないし、海の近く以外でどこに住めばいいのかも分からない(笑)。長くビーチのすぐ側に住んでいて、これからも出来る限り長くサーフィンをするつもりだ。都会、内陸の山や砂漠地帯とどれも好きだけど、今も昔もサーフィンを愛している。サーフィンは私の人生そのものだし、それが唯一の生きる道に間違いない。

インタビュー/川添 澪(かわぞえみお)●神奈川県鎌倉市出身・在住。カリフォルニア州立大学サンディエゴ校・サーフィン部卒。日本の1stジェネレーションのサーファーを父に持ち、幼い頃より海外のカルチャーに邂逅。90年初頭から10年間に渡り、カリフォルニア・サンディエゴ〜マリブに住み、ロングボード・リバイバルを体感。帰国後はON THE BOARD編集長に就任し、GLIDE他の雑誌媒体を手がける。これまで独自のネットワークでリアルなカリフォルニアのログ、オルタナティブサーフシーンを日本に紹介。