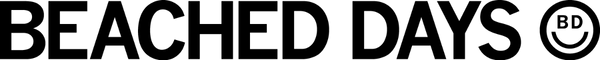第10回 マット・チョナスキー Art of Trim〜サーフカルチャーの昇華
Share
クラシックなロングボードのライディングだけでなく、背景にあるヒストリーやカルチャーにも精通。ロガーとしての枠を超え、近年ではビッグウェイブにも果敢にチャージする傍ら、WSLのコメンテーターとしてショートボードやジュニア・コンテストでも活躍するマット・チョナスキー。
記念すべき第10回は、クラシックカーやローライダーを所有し、オーストラリア出身でありながら、SO CAL〜カリフォルニア・スタイルを敬愛するMR. WAXHEADの登場です。

(Narrabeen Photo: Ian Bird)
昨年から長いこと地元のオーストラリア・シドニーを離れて、世界各地を色々と飛び回っているみたいだね。
11月末にWSL(ワールドサーフリーグ)のQSイベントのコメンテーターの仕事でセントラル・カリフォルニアに来て、シークレットスポットですごくいい波を当てたんだ。その後はクリスマスの時期にフィアンセと彼女の親戚がいるエルサルバドルに向かい、この時期には珍しいサウスとウエストからのスウェルの素晴らしい波に遭遇した。その後は同じウェストスウェルを追いかけカリフォルニアに戻り、数十年に一度と言われる巨大なリンコンでサーフしたんだ。おそらく20ftはあったんじゃないかな。年明けはハワイ・ノースショアに行って、サンセットビーチのまあまあサイズのある波でサーフした。

(Sunset , Jan '24 Photo:Dani Toro)
リンコンやサンセットのエピックなセッションの様子は君のインスタにも上がっていたね。ロングボーダーの域を超えて、最近はデカい波にもチャージしているのは何かきっかけがあったの?
世界はコロナによって世の中の仕組みも含めて大きく変わったと思うけど、実際にコロナ禍を経て自分自身のライフスタイルも大きく変わったし、人生を見直す機会になったんだ。
2019年のWLT(ワールド・ロングボード・ツアー)を3戦周り、翌年2020年第1戦のヌーサは7位だった。ヌーサの次はカリフォルニアのウェイブプールで、その後はマリブ。マリブでのパフォ−マンスは結構自信があったから、ワールドタイトルを見据えてコンペにフォーカスしていた。だけど、その後コロナで世界はロックダウン。オーストラリアでは自宅から半径5km以上の移動は禁止され、国外に出るさえ不可能となった。だから必然的にホームでの時間が増えたけど、結果としてシドニーには歴史的なビッグウェイブが連日押し寄せ、これまでの人生で最高のコンディションが2年に渡って続いたんだ。2週間毎に10フィート・オーバーのスウェルがやって来て、2フィート以下になることがないほど。
 これまで自分はロングボードにハマっていて、ビッグウェイブのサーフィンも好きだったけど、決して多くの経験があったわけじゃない。ロックダウンの期間はコンペモードから離れて、ホームでシングルやクアッドのガンなど様々なスタイルのボードでビッグウェイブに乗ったり、ロングボードでデカいバレルに入るなど、これまでにないアプローチで自分自身の可能性を開拓していた。その瞬間、これまで為し得なかった境地に到したんだ! 長い間サーフィンを追い求めてきて、本当に良かったと思った瞬間さ。
これまで自分はロングボードにハマっていて、ビッグウェイブのサーフィンも好きだったけど、決して多くの経験があったわけじゃない。ロックダウンの期間はコンペモードから離れて、ホームでシングルやクアッドのガンなど様々なスタイルのボードでビッグウェイブに乗ったり、ロングボードでデカいバレルに入るなど、これまでにないアプローチで自分自身の可能性を開拓していた。その瞬間、これまで為し得なかった境地に到したんだ! 長い間サーフィンを追い求めてきて、本当に良かったと思った瞬間さ。
コロナで世界の動きが止まってしまい、人々が失ったものも大きかったかもしれない。でも結果的には自分にとって大好きなこと……クラシックカーやサーフィンの重要性をより感じることができたし、ビッグウェイブの世界に踏み込む機会も与えてくれたんだ。かつて、ボブ・マクタビュシュらパイオニア達が60年代から70年代にかけて世界のビッグウェイブを開拓したようにね。
いまはまたカリフォルニアに滞在中? カリフォルニアにはコンテスト以外でも頻繁に訪れているよね。
いまはWSLのワールド・ジュニア・チャンピオンシップのコメンテーターのためにオーシャンサイドに滞在中。カリフォルニアは自分にとってのBirth of Coolそのもので、多くのインスパイアを受けている。クラシックカーやサーフスタイル、街にはサーフヒストリーがあって、来る度にタイムトリップした気分になる。もちろん時代は変わっていくけど、自分にコネクトするものがあるんだ。もちろん生まれ育ったオーストラリアも大好きだし、素晴らしいサーフカルチャーもある。でもつくづく自分はユニークなオーストラリアンだと思うよ。(笑)。
世界各地を廻りながら、家業の車のビジネスは続けているの? 所有する車は?
ああ、Taylor & Botham Bodyworks という名で、古い車のレストアなどを手がけている。いま乗っている車は、1971年製VWピックアップトラップ、1961年製シェビー・パネルバンのローライダー、1971年製フォードエコノラインのサーフカーの計3台。

WSLのコメンテーターの仕事はどういった経緯で、何年くらいやっているの? ロングボードだけじゃなく、ショートボードでも関わっているんだね。
かれこれ5年になるかな。2022年からは本腰を入れ、より多くのWSLのイベントに参加しているよ。元々サーフィンの歴史やカルチャーは大好きで、もちろん自分自身でサーフィンするのも大好き。個人的にはサーフィンは必ずしもスポーツではなく、パフォーマン・アートと考えている。ヒート後のインタビューでも使っているサーフボードについて聞いたり、バックグラウンドについての話しをみんなに伝えることは楽しい。他の人とは違うプロサーフィンの側面を見せることが出来ているんじゃないかな。大会に関わるからには自分が参加することによって、より楽しめるようにしていきたい。外部からただ文句を言って、見てるだけじゃなくてね。WSLやみんながが自分の視点を興味深いと思ってくれる限り、協力して行きたいと思っている。
コンペではロングボーダーのコーチングもしているよね? 女性専門のワケは?
その理由は自分がまだコンテストで戦っているからで、男性の対戦相手に戦略を教えてもね(笑)。過去5、6年でコーチングしてきたのは、若いオージーだけでなく、ブラジルのクロエ・カロモン、ハワイのホノルア・ブルームフィールドとかチャンピオンも多数。彼女たちはサーフィンについての知識もあり、カルチャーにも精通している。私にとってそれがすべてで、その繋がりを感じたくない人にはコーチすることはできないんだ。私たちが波に乗ること、意味するものは人によって異なるけど、スピリチュアルなダンスであることは間違いない。自身のスキルの向上のためにコンペであってもフリーサーフィンであってもその繋がりを感じることができれば、サーフィンはより価値のあるものになるから。そして最終的には、より良いサーフィンの環境を作っていきたいと思っているんだ。

(w/Chloe Calmon)
ロングボードにハマったきっかけは?
自分の両親は元々ポーランドからの移民で、サーフィンをしない家庭環境で育った。シドニーのビーチのすぐ側に住んでいたから、ジュニア・ライフガードに入って父親と一緒にサーフィンを始めた。最初のボードは80'sのホットバタードの分厚い5'6"のスラスターで、サーフィンを始めるにはベストなボードだった。
最初はショートボードで必死に波に乗っていたんだけど、いつしかいつものビーチに来るロングボーダー達が小さい波でも優雅に波を乗っている姿に魅了された。当時はよく分かっていなかったけど、それが1964年のワールドチャンピオンのミジェット・ファレリーだった。彼は毎朝1ラウンドをこなし、仕事に行っていた。後に自分も父親のロングボードを借りて、見よう見まねで彼のスタイルをコピーしていた。ラッキーなことに自分のホームではトム・キャロルやダミアン・ハードマン、テリー・フィッツジェラルド、サイモン・アンダーソンと言ったレジェンドから、ネイザンヘッジ、ネイザン・ウェブスタ−、ルーク・ステッドマンといったスターに囲まれてサーフィンしていた。でもあの朝のミジェット・ファレリーのインパクトに勝るものはなかった。カリフォルニアや日本に遅れを取っていたオーストラリアは、90年代はもちろん、2000年初頭もロングボードは人気がなかったし、クールじゃなかった。でも自分はクラシック・ロングボードが持つ、時代に流されないクリエイティブなスタイルに虜になったのさ。

ロングボードを本格的に始めて、最初はKeyo Surfboardsのジョン・ギル、その後にロビン・キーガルと知り合い、Gato Heroに乗っていたんだ。彼はカリリフォルニア・ガイだけど、オーストラリアのサーフカルチャーにも精通していて、ユニークなスペースシップ・スタイルのサーフボードを作っていた。つまりロングボードが進化を止めた1967年以降のサーフボードのデザイン。ニューエイジだけど、後の2+1のハイパフォーマンス・ロングボード(HP)とは一線を画すもの。自分はHPスタイルのロングボーディングは全くもって好きじゃない。なぜなら私がシングルフィン。ロングボードに乗る理由のすべては、トリムとグライドにあり、HPに乗っても決して味わえないもの。真のロングボーディングは、フロー、スピード、トリム、そしてグライドなんだ。
60年代から活躍するパイオニア・サーファーであり、レジェンド・シェイパーのボブ・マクタビッシュとの出会いは?
ボブとの出会いも、ロビーと一緒にヌーサに行ったのがきっかけなんだ。その時も、「オー、ボブ!」「オー、WAXHEAD(マットの愛称)! まるで私のMINI MEみたいだな」って(笑)。その出会いから約6ヶ月後、ボブのMcTavish Surfboardsがこれまでの海外向けの大量生産のスタイルからリブランドすることになった。ちょうどロビーもブランドをオーストラリアの仲間のディストリビューターに渡すことになり、自分も彼のボードに乗る必要が無くなったんだ。そしてボブがボードを作ってくれることになり、60年代当時のテンプレートを復刻させてくれることになった。
9'3"のインボルブメント・スタイルとボブがハワイで実際に乗っていた9'10”Dフィンガン、7'6"のトラッカーモデル、マット・トラッカーと呼ばれる計3本のシングルフィン。そしてこれらは、これまで所有していた中で最高のボードで、もちろんいまも大事にしている。イクイップメントの品質と目的が一致する唯一無二のもので、それから13年に渡り、チームの一員で彼のデザインに乗ることが出来るのはこの上ないラッキーなこと。これまで6つのボード・デザインに携わり、なかでもインボルブメント・スタイルはボブとの関係性で完成させ、自分が国内外で初めて乗り始めたデザインの一つ(注:現在トレンドのいわゆるPIGスタイルのログ)。
これまでKeyo、Bennet、ロビー・キーガル、ボブ・マクタビッシュと世界のベスト達とボードデザインをしてきて、レイルからロッカー、フィン・ポジションとありとあらゆることに関して、自分のサーフボードIQ、フィンIQは高まり、サーフィンのヒストリーを身にもって体感することが出来たことにとても感謝している。

(w/Bob McTavish)
君がやっているArt of Trimとは?
この2、3年の間、様々なコンディションでクラシックなシングルフィンのロングボード、ショートボード、ガンに乗ってきた。幸いコロナでサーフィンに向き合う時間が充分にあって、極限まで自分と向き合うことができ、Art of Trimのプロジェクトをまとめることができたんだ。
世界中で多くの人がサーフィンを始め、今ではたくさんの人が情報を求めて私に連絡してきている。でも自分はいわゆる一般的なコーチングはしていないんだ。一般的なサーフスクールはサーフボードに立つ方法を教えるけど、カルチャーや歴史、理論なんかは教えてくれない。それがThe Art of Trimを始めた理由さ。
ハングテンのやり方を技術的側面からレクチャーするのはなく、なぜ波のこの部分でハングテンをするのか、それはどこから来ているのかを理解してもらう。フィン一つにとっても、ドルフィンからの起源やジョージ・グリーノウについての話しをする。色々な素材を提供し、バックストーリーも伝え、カルチャーとしての側面を与えることによって、人々のサーフィンはアートとして素晴らしいものになるから。
The Art of Trimとは、まず良いサーフィンのファンであること。マインド、ボード、波がひとつになると、美しい光景が広がる。まだまだ小さい規模のビジネスだけど、オンライン、対面と問わず、多くの人とサーフィンの素晴らしさを共有していきたいと思っている。

2024年の予定は?
WLTツアーがおそらく4戦あるから、それに参加する。あと世界各地で開催されるWSLコンテストのコメンテーターの仕事も続けて行くよ。オーシャンサイドの後はフィリピンに行く。ここ数年、アジア各国では、ショートボード、ロングボードとサーフィンは盛んになって、独自の発展を遂げているのをヒシヒシと感じるよ。フィリピン、インドネシア、タイ、台湾と各地ではサーフカルチャーを理解し、スタイリッシュなロングボーダーも育っている。もうすぐ数年間のフッテージをまとめたムービーが完成する予定だから、近いうちに日本に上映しに行きたいと思っているんだ。
君にとってサーフィン、そしてビーチとは?
フリーダムさ! 自分にとって、サーフィンは表現の手段でもあり、人生を豊かにしてくれるもの。人生は一度きり。だから自分の心に正直に、悔いのないようにパッションを追い続けてね。

マット・チョナスキー●1988年生まれ、オーストラリア・シドニー出身、在住。アーリーティーンよりクラシック・ロングボーディングで頭角を現す。レジェンド達との交流も深く、サーフカルチャーやヒストリーに精通。ビンテージボードだけでなく、クラシックカーも複数台所有し、オーストラリアンながらSO CALスタイルを地で行くひとり。近年は往年のクラシックなスタイルでビッグウェイブにチャージ。各国のWLTコンテストに参戦するだけでなく、ショートボード、ロングボードとジャンルを問わずWSLのコメンテーターとしても活躍し、サーフィンの楽しさ、美しさを伝えている。
Instagram: @thewaxhead @theartoftrim
インタビュー/川添 澪(かわぞえみお)●神奈川県鎌倉市出身・在住。カリフォルニア州立大学サンディエゴ校・サーフィン部卒。日本の1stジェネレーションのサーファーを父に持ち、幼い頃より海外のカルチャーに邂逅。90年初頭から10年間に渡り、カリフォルニア・サンディエゴ〜マリブに住み、ロングボード・リバイバルを体感。帰国後はON THE BOARD編集長に就任し、GLIDE他の雑誌媒体を手がける。これまで独自のネットワークでリアルなカリフォルニアのログ、オルタナティブサーフシーンを日本に紹介。